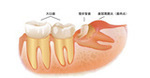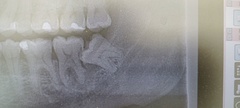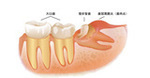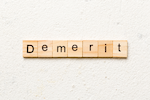親知らずの抜歯後に痛みが続くことは、多くの人が経験する不安な問題です。抜歯後、痛みが一定の期間続くことは通常の経過であることもありますが、場合によっては異常な状態を示すこともあります。このブログ記事では、親知らず抜歯後の痛みが続く理由とその原因、そしてどのように対処するかについて詳しく解説します。
1. 親知らずを抜歯したのに痛みが続くのはなぜ?
親知らずの抜歯後、痛みが続く理由としていくつかの原因が考えられます。通常、親知らずの抜歯後は数日から1週間ほど痛みが続くことがありますが、痛みが長引く場合は何かしらの異常がある可能性があります。
抜歯後の痛みの一般的な経過(通常は何日で治る?)
親知らずを抜歯した後、痛みは通常数日間続きます。具体的には、最初の24時間は強い痛みがあり、その後2~3日程度で痛みが和らぎます。痛みが完全に治まるまでには、約1週間程度かかることが一般的です。しかし、痛みの感じ方には個人差があり、場合によっては1週間を超えて痛みが続くこともあります。
痛みが長引くのは異常?
痛みが1週間以上続く場合や、突然強い痛みが再発する場合は、異常がある可能性があります。このような場合は、早期に歯科医院を受診することをお勧めします。特に、強いズキズキとした痛みや腫れがある場合、感染症や炎症の兆候かもしれません。
どのような場合に歯科医院を受診すべきか?
次のような症状が現れた場合、早急に歯科医院を受診することが重要です。
- 抜歯後1週間以上経過しても痛みが引かない
- 激しい痛みが突然発生する
- 顎の腫れや発熱が見られる
- 口の中に異常な臭いがする
- 出血が続く
- しびれや麻痺の症状が現れる
これらの症状は、早期の治療が必要な場合が多いです。
2. 親知らず抜歯後の痛みが続く主な原因

親知らず抜歯後の痛みが長引く原因として、いくつかの主な理由が考えられます。それぞれの原因に応じた適切な対処法を知ることが、痛みを軽減するために重要です。
2-1. ドライソケット(抜歯後の治癒不良)
ドライソケットとは?
ドライソケットは、抜歯後に傷口の血餅(けっぺい)が正常に形成されず、傷が乾燥してしまうことで発生する状態です。血餅は傷口を保護する役割を果たし、治癒を助けますが、これが取れてしまうと骨が露出して激しい痛みを引き起こします。
どんな症状が出る?(ズキズキとした激痛・骨が露出)
ドライソケットでは、強いズキズキとした痛みが特徴です。痛みは抜歯後2~3日を過ぎた頃に始まり、徐々に悪化します。痛みが耳や目、頭部に放散することもあります。さらに、傷口に骨が露出し、目視で確認できる場合もあります。
なりやすい人の特徴と予防法
ドライソケットになりやすい人には、喫煙者や口腔内の衛生状態が悪い人、過度な運動を行っている人などが含まれます。予防するためには、抜歯後24時間は血餅を安定させるために激しい運動や喫煙を避け、傷口を清潔に保つことが大切です。
2-2. 細菌感染(抜歯後の化膿)
傷口に細菌が入るとどうなる?
抜歯後の傷口に細菌が入り込むと、感染症を引き起こすことがあります。感染が広がると、痛み、腫れ、膿が出ることがあります。
化膿するとどんな症状が出る?
化膿が進行すると、強い痛みと共に膿が傷口から出ることがあります。また、発熱や顎の腫れが現れることもあります。
抗生物質が必要になるケース
化膿がひどくなる前に抗生物質を使うことが重要です。感染が広がらないように、歯科医院で診察を受け、抗生物質を処方してもらうことが必要です。
2-3. 顎の炎症や骨膜炎
抜歯後の顎の腫れと痛みの原因
親知らずの抜歯後に顎の腫れや痛みが続く場合、顎の骨に炎症が起こることがあります。この炎症は「骨膜炎」と呼ばれ、感染症によって引き起こされることが多いです。
骨膜炎を防ぐには?
骨膜炎を防ぐためには、抜歯後のケアをしっかり行い、傷口が清潔であることを確認することが大切です。
2-4. 神経がダメージを受けた場合
親知らず抜歯後のしびれ・麻痺のリスク
親知らずを抜歯する際に、近くの神経にダメージが加わることがあります。これにより、抜歯後にしびれや麻痺が生じることがあります。特に、下顎の親知らずの抜歯では神経を傷つけるリスクがあります。
しびれが治らない場合の対処法
しびれが長期間続く場合は、神経に対する適切な治療を受ける必要があります。治療には、リハビリや再手術が必要な場合もあります。
2-5. 歯茎や周辺組織の炎症
炎症による痛みと腫れの特徴
抜歯後の歯茎や周辺組織に炎症が起きることがあります。これにより痛みや腫れが発生します。この場合、痛みはしばしば時間とともに和らぎますが、炎症がひどくなる前に適切な処置をすることが重要です。
口腔ケア不足で起こるトラブル
口腔ケアが不十分な場合、傷口に細菌が繁殖し、炎症や感染が引き起こされることがあります。抜歯後は特に清潔を保つことが重要です。
3. 親知らず抜歯後の痛みを和らげる方法【自宅でできる対処法】
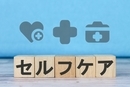
親知らずの抜歯後に痛みが続く場合、自宅でできる対処法もあります。以下に、痛みを和らげる方法をご紹介します。
市販の痛み止めを正しく使う
市販の痛み止めを適切に使用することで、痛みを軽減することができます。服用のタイミングや使用方法については、説明書をよく読み、過剰に使用しないようにしましょう。
うがい・歯磨きの注意点(口の中を清潔に保つコツ)
抜歯後は、うがいや歯磨きによって傷口に細菌が入り込まないように注意が必要です。優しくうがいをし、歯磨きは傷口を避けて行いましょう。
腫れや痛みを抑える冷却のやり方
冷たいものを使って腫れを抑えることが効果的です。アイスパックを患部に当てて、腫れや痛みを和らげましょう。
食事や生活習慣で気をつけること
抜歯後は、柔らかい食べ物を選び、刺激の強い食べ物や飲み物は避けましょう。また、タバコやアルコールは抜歯後しばらく避けることが推奨されます。
4. いつまで痛みが続いたら歯医者に行くべき?
痛みが1週間以上続く場合や、突然痛みが強くなる場合、何らかの異常がある可能性が高いです。放置しておくと症状が悪化することがありますので、早めに歯科医院で診てもらうことが重要です。
「3日以上ズキズキする」「1週間たっても痛みが消えない」などの危険サイン
痛みが3日以上続く、もしくは1週間経過しても痛みが引かない場合は、異常を示唆している可能性が高いです。この時点で歯科医院を受診しましょう。
放置するとどうなる?(悪化のリスク)
放置すると、化膿や感染症、骨の損傷など、さらに悪化するリスクがあります。最悪の場合、再手術や追加の治療が必要になることもあります。
受診するとどんな治療をする?(洗浄・抗生物質・再処置など)
歯科医院での治療には、傷口の洗浄や、必要に応じて抗生物質の処方、再処置が行われることがあります。
5. 親知らず抜歯後の痛みを防ぐためにできること

抜歯後の痛みを防ぐためには、適切なセルフケアと生活習慣が重要です。抜歯後すぐに気をつけるべきポイントや術後のケアについて詳しく解説します。
抜歯後すぐに気をつけるべきポイント
抜歯後24時間は安静にして、激しい運動や喫煙を避けましょう。血餅が安定するまで、傷口を触らないように注意してください。
術後のセルフケアと生活習慣
日常生活では、傷口を清潔に保つことが大切です。うがいや歯磨きは優しく行い、痛みや腫れを抑えるために冷やすことも有効です。
再発防止のための歯科医院でのチェック
再発防止には定期的な歯科医院でのチェックが重要です。抜歯後の経過を確認してもらい、異常があれば早期に対処してもらいましょう。
6. 【よくある質問】親知らず抜歯後の痛み・腫れ・違和感について

Q1. 親知らずを抜いてから1週間たっても痛みが引かないのは異常?
はい、1週間たっても痛みが引かない場合は、何らかの異常が考えられます。早めに歯科医院を受診しましょう。
Q2. 親知らずを抜いた後に口臭がするのはなぜ?
口臭がする場合、感染症や傷口の清潔さが不十分なことが原因かもしれません。こまめに口腔ケアを行い、状態を確認することが必要です。
Q3. 抜歯後に腫れが長引くことはある?何日で治る?
腫れが長引く場合は、感染症や炎症が原因の可能性があります。通常は1週間程度で治りますが、長引く場合は受診を検討しましょう。
Q4. 抜歯後に白いものが見えるのは大丈夫?(ドライソケットとの違い)
白いものが見える場合、それは血餅が取れて骨が露出した可能性があります。ドライソケットの兆候かもしれませんので、歯科医院で確認を受けましょう。
Q5. 抜歯後に痛み止めを飲んでも効かない場合、どうすればいい?
痛み止めが効かない場合は、異常がある可能性があるため、早めに歯科医院を受診し、対処法を確認することが重要です。
Q6. 仕事・学校は何日休むべき?
仕事や学校は、痛みや腫れがひどい場合は1~2日休むことをおすすめします。痛みが軽減したら無理なく復帰できます。
Q7. お酒やタバコはいつからOK?
お酒やタバコは、抜歯後少なくとも1週間は避けるようにしましょう。傷口の治癒を妨げる原因となります。
Q8. 抜歯後に運動してもいい?
抜歯後は1~2日安静にし、その後も過度な運動は避けることが推奨されます。激しい運動は血圧の上昇や感染症のリスクを高めます。
Q9. 親知らず抜歯後、何を食べるべき?
抜歯後は、柔らかい食べ物や温かい食べ物を選びましょう。硬い食べ物や刺激の強いものは避けることが大切です。
7. まとめ|痛みが続く場合は無理せず歯科医院へ相談を!

親知らずの抜歯後、痛みが続くことはありますが、痛みが長引く場合や強い痛みが再発する場合は、早めに歯科医院を受診することが大切です。早期の対処で、症状の悪化を防ぎ、快適な回復を促進することができます。痛みが続く場合は無理せず専門家に相談し、適切な治療を受けることをお勧めします。
口腔外科・親知らずの抜歯のことなら、名古屋市天白区の歯医者・歯科・口腔外科・親知らずの抜歯のイナグマ歯科までご相談ください。
監修 岡山大学 歯学博士 厚生労働省認定 歯科医師臨床研修医指導医 稲熊尚広
イナグマ歯科の予約 →詳細はこちら