唾石症とは?

唾石症(だせきしょう)とは、唾液を分泌する唾液腺内に硬い石(唾石)ができる疾患のことです。唾液腺は、口腔内の乾燥を防ぎ、食べ物の消化を助ける唾液を分泌する重要な役割を果たしています。しかし、唾液腺内で唾液がうまく排出されず、唾液成分が固まることで唾石が形成されることがあります。唾石症はしばしば痛みを伴い、場合によっては慢性的な腫れを引き起こすこともあります。
唾石症の基本情報と原因
唾石は通常、唾液に含まれるカルシウムやリン酸塩、ビリルビン、ムコ多糖などが沈着し、固まりながら形成されます。この過程は、唾液の分泌量が減少したり、唾液腺が閉塞されたりすることで促進されます。原因としては以下のようなものが考えられます:
-
唾液の分泌減少: 脱水症状や薬物の副作用(抗ヒスタミン薬など)、あるいは加齢に伴う唾液分泌の減少。
-
唾液腺の閉塞: 唾液腺に細菌が感染し、膿がたまることで唾石ができやすくなることがあります。
-
慢性の口腔乾燥症: 口腔内が乾燥することで唾液の流れが滞り、唾石ができやすくなります。
-
口腔内の異常: 歯科的問題(虫歯、歯周病など)が唾液腺に影響を与えることもあります。
唾石が形成されることで、唾液の流れが阻害され、口腔内で不快感や痛みを引き起こす場合があります。
唾石ができる部位とその症状
唾石は主に以下の3つの唾液腺で発生します:
-
顎下腺(下顎の唾液腺)
-
唾石症の発生率が最も高い部位です。顎下腺は、口の中で唾液を分泌する主要な腺であり、唾石はこの部位で最もよく見られます。
-
-
耳下腺(耳の下にある唾液腺)
-
唾石は稀に耳下腺でも見られますが、顎下腺よりも発生頻度は低いです。
-
-
舌下腺(舌の下にある唾液腺)
-
唾石は舌下腺にもできることがありますが、一般的には顎下腺に比べて少ないです。
-
唾石ができると、以下のような症状が現れます:
-
痛みや腫れ: 唾石が唾液腺を圧迫すると、痛みや腫れを引き起こします。特に食事中や唾液分泌が活発になる時に痛みが増すことがよくあります。
-
口腔内の乾燥感: 唾液がうまく分泌されなくなるため、口の中が乾燥することがあります。
-
口臭: 唾液の流れが滞ることで、細菌が繁殖し、口臭が発生することがあります。
口のほほに唾石ができる理由
口のほほに唾石ができる原因としては、主に顎下腺に関連するものが多いです。顎下腺は、下顎の内側にある小さな開口部を通じて唾液を分泌しますが、この開口部が狭くなると、唾液の流れが滞りやすくなります。唾液の流れがうまくいかないと、唾石が形成されるリスクが高まります。
また、食事中やおしゃべりをしている際には、唾液の分泌が活発になるため、これが唾石形成を促進することもあります。その他、口腔内の感染や歯周病も唾石症を引き起こす要因となることがあります。
唾石症はがんの原因になるのか?

唾石症は、一般的にはがんの直接的な原因にはなりません。しかし、唾石症と口腔がんの間に何らかの関連があるのかについては、いくつかの研究があります。唾石症自体ががんを引き起こすことは稀ですが、唾石症を放置しておくことで、炎症が慢性化し、がんのリスクが高まる可能性があることは理解されています。
唾石症とがんの関係性
唾石症自体ががんを直接引き起こすわけではありませんが、長期間にわたる唾石症が引き起こす慢性的な炎症や感染が、口腔がんなどのリスクを高める可能性は指摘されています。唾石症が引き起こす口腔内の炎症が慢性化すると、局所的な免疫系の障害が生じ、細胞の異常な増殖を促すことがあるため、がんのリスクが高まるとされています。
唾石ががん化するリスク
唾石が直接的にがん化することは少ないですが、唾石が引き起こす慢性の炎症が、長期間続くことでがん化のリスクを高める可能性があります。特に、唾石症が長期にわたって放置されると、唾液腺内で炎症や感染が続き、それが細胞の異常な増殖に繋がることがあります。
唾石症が口腔がんに影響を与えるメカニズム
唾石症が口腔がんに影響を与えるメカニズムは、主に慢性的な炎症と免疫機能の低下に関連しています。炎症が長期化すると、免疫細胞が正常に機能しなくなり、異常な細胞の増殖を抑える力が弱くなります。このような状態が続くことで、がん細胞が発生しやすくなることがあります。
唾石症の症状と進行状況

唾石症は初期段階では無症状であることが多く、症状が現れる頃には唾石が大きくなっていることがよくあります。唾石の進行状況によって症状の程度も変わります。
唾石症の初期症状と進行のサイン
初期段階では、唾石が小さくて症状が軽いため、気づかれにくいことがあります。しかし、唾石が大きくなるにつれて以下のような症状が現れることがあります:
-
痛みや腫れ: 唾石が大きくなると、唾液腺が圧迫されて痛みや腫れが現れます。
-
口の乾燥: 唾液の分泌が減少するため、口の中が乾燥しやすくなります。
-
口腔内の不快感: 食事中や会話中に不快感を感じることがあります。
唾石が引き起こす痛みや腫れ
唾石が唾液腺を圧迫すると、唾液の流れが滞り、痛みや腫れが発生します。特に食事中や唾液分泌が活発になる時には、痛みが強くなることがあります。進行すると、腫れが顕著になり、顔が膨らむこともあります。
放置すると悪化する可能性について
唾石症を放置すると、唾石がさらに大きくなり、痛みや腫れが増すことがあります。また、感染が広がり、膿がたまることで膿瘍が形成されることもあります。最悪の場合、唾液腺が壊死することがあり、手術が必要になることもあります。
唾石症の治療法
唾石症の治療方法は、唾石の大きさや症状の程度に応じて異なります。治療は薬物療法から手術まで、様々な方法があります。
唾石症の治療方法(薬物治療・手術など)
唾石が小さい場合は、薬物療法や温罨法(温めて刺激を与える方法)で唾石を取り除くことが可能です。薬物療法では、唾液の流れを促進する薬や抗生物質を使用することがあります。唾石が大きくなると、手術が必要となる場合があります。
手術なしで治療する方法はあるのか?
手術なしで治療できる場合もあります。小さな唾石であれば、唾石をマッサージして押し出すことができる場合もあります。その他、唾液分泌を促進する薬や温罨法を使用することで、唾石を取り除けることもあります。
唾石症の治療後の注意点
唾石症の治療後は、再発を防ぐために定期的な口腔ケアを行うことが重要です。また、食生活の改善や水分摂取を心がけ、口腔内の乾燥を避けることが予防に繋がります。
唾石症の予防法
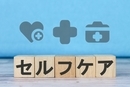
唾石症を予防するためには、日常的な口腔ケアと健康的な生活習慣が欠かせません。
唾石症を予防するための口腔ケア
口腔ケアは唾石症の予防において非常に重要です。歯磨きやうがいをしっかり行い、口腔内の衛生状態を保つことが大切です。また、適度に唾液を分泌させるために、ガムを噛むことや水分を頻繁に摂取することも効果的です。
食生活や生活習慣の改善
食生活や生活習慣も唾石症の予防に大きな影響を与えます。唾液の分泌を促進するためには、バランスの取れた食事と十分な水分摂取が必要です。また、タバコやアルコールを避けることが、口腔内の健康を保つために重要です。
定期的な口腔チェックアップの重要性
定期的な歯科検診を受けることも、唾石症の予防には欠かせません。歯科医師が早期に異常を発見し、適切な治療を行うことができます。
よくある質問(FAQ)

唾石症は痛みを伴うのか?
唾石症は痛みを伴うことがあります。特に唾石が唾液腺を圧迫すると、食事中や唾液分泌が活発な時に痛みが強くなることがあります。
唾石ががん化する可能性は本当にあるのか?
唾石症が直接がんを引き起こすことは稀ですが、長期間放置した場合、慢性の炎症が続き、それが口腔がんのリスクを高める可能性があります。
唾石症を予防するための効果的な方法は?
唾石症を予防するためには、口腔ケアの徹底や水分摂取、定期的な歯科検診が効果的です。
唾石症の治療にはどれくらいの時間がかかるのか?
治療の内容によりますが、薬物療法や手術が必要な場合、数日から数週間程度で回復することが一般的です。
唾石症と口腔がんの違いは?
唾石症は唾液腺に唾石が形成される病気であり、口腔がんは口腔内の細胞が悪性化する病気です。唾石症が直接的に口腔がんを引き起こすことはありませんが、慢性的な炎症ががんのリスクを高める可能性があります。
唾石症と口腔がんの早期発見
唾石症を早期に発見するためには、定期的な口腔ケアと歯科検診が大切です。唾石症の早期発見と治療によって、がん化のリスクを減らすことができます。
がん予防のための口腔ケアの実践法
がん予防には、日々の口腔ケアと生活習慣の改善が欠かせません。タバコやアルコールの摂取を控え、バランスの取れた食事と水分補給を心がけましょう。
まとめ

唾石症は口腔内の唾液腺に唾石が形成される病気で、適切な治療と予防が重要です。唾石症が進行すると、口腔がんのリスクを高めることがあるため、早期発見と治療が大切です。口腔ケアや生活習慣を改善することで、唾石症の予防や再発防止に繋がります。
口腔外科・口腔癌のことなら、名古屋市天白区の歯医者・歯科・口腔外科・口腔癌診断のイナグマ歯科までご相談ください。
監修 岡山大学 歯学博士 厚生労働省認定 歯科医師臨床研修医指導医 稲熊尚広
イナグマ歯科の予約 →click here
口腔外科のページ→click here
唇のできもののページ →click here
歯科定期検診 →click here


