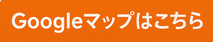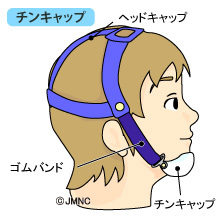舌のぶつぶつや白いできものは口腔がん?症状・見分け方・予防法を歯科医が解説|名古屋市天白区 イナグマ歯科

こんにちは、名古屋市天白区の歯医者・歯科・口腔外科・口腔がん診断のイナグマ歯科です。
院長:岡山大学 歯学博士 厚生労働省認定 歯科医師臨床研修医指導医 稲熊 尚広
舌のぶつぶつや白いできもの、それって大丈夫?口腔がんの可能性と見分け方を徹底解説
「舌の先に白いぶつぶつがあるけど、これって何だろう…?」 「口の中に口内炎とは違うできものができた。もしかして、がん…?」
口の中、特に舌に異変を見つけると、誰でも不安になるものです。インターネットで検索すると、「口腔がん」という怖い言葉が目に入り、さらに恐怖を煽られるかもしれません。
しかし、ご安心ください。舌にできるできもののほとんどは、心配のいらない良性のものです。ただ、中には治療が必要なものや、ごく稀に口腔がんの兆候である場合もあります。
この記事では、口の中のできものや異変について、不安を抱えるあなたが正しい知識を身につけ、適切な判断ができるように、専門的な視点からわかりやすく解説します。
なぜ舌に「ぶつぶつ」や「白いできもの」ができるのか?その原因と種類

舌にできる異変は、見た目や症状によって様々な原因が考えられます。まずは、代表的なものをいくつか見ていきましょう。
1. 口内炎(アフタ性口内炎)
最も一般的で、ほとんどの人が経験したことのある口の中のトラブルです。
-
特徴: 白っぽく、中央がくぼんだ丸い潰瘍で、周囲が赤く炎症を起こしている。触れると強い痛みがある。
-
原因: ストレス、睡眠不足、栄養バランスの偏り(特にビタミンB群の不足)、疲労などが主な原因とされています。
-
対処法: 通常、1〜2週間で自然に治癒します。うがい薬や軟膏を使用すると、痛みが和らぎ、治りが早まることがあります。
2. カンジダ性口内炎
カビの一種であるカンジダ菌の増殖によって起こる感染症です。
-
特徴: 舌や頬の粘膜に白い苔のようなものが付着し、ガーゼなどで拭うと簡単にはがれる。はがした部分から出血することもある。
-
原因: 免疫力の低下、抗生物質の長期服用、唾液の分泌量低下などが引き金になります。高齢者や、ステロイド吸入薬を使用している人に多く見られます。
-
対処法: 歯科医院や耳鼻咽喉科で、抗真菌薬(抗カビ剤)の軟膏や内服薬が処方されます。口腔内の清掃も重要です。
3. 舌乳頭炎(ぜつにゅうとうえん)
舌の表面にある、味を感じるための小さな突起(舌乳頭)が炎症を起こした状態です。
-
特徴: 舌の縁や先に、赤く小さなぶつぶつができる。特に辛いものや熱いものを食べたときにピリピリとした痛みを感じやすい。
-
原因: 刺激の強い食べ物や飲み物、熱いものによる火傷、ストレス、歯ブラシでの強い摩擦などが原因となります。
-
対処法: 刺激物を避け、安静にしていれば数日で自然に治ることがほとんどです。
口腔がんの可能性を疑うべきサインとは?

前述したような良性の症状に対し、もし以下のような特徴が1つでも当てはまる場合は、自己判断せず、すぐに専門医(歯科口腔外科、耳鼻咽喉科など)を受診することが重要です。
【要注意!口腔がんのセルフチェックリスト】
-
2週間以上治らない口内炎: 通常の口内炎は長くても2週間程度で治ります。それ以上長引く場合は要注意です。
-
痛みがほとんどない: 口内炎は強い痛みを伴いますが、口腔がんの初期は痛みがほとんどないことがあります。
-
硬いしこりやただれ: 舌や歯肉、頬の粘膜に、指で触ると硬いしこりがある、またはただれている部分がある。
-
白い斑点、赤い斑点: 擦っても取れない白い斑点(白板症)や、赤い斑点(紅板症)がある。特に紅板症は、がん化するリスクが非常に高いとされています。
-
出血や痺れ: 理由なく出血したり、舌や口の周りに痺れや麻痺を感じる。
-
顎の下や首のリンパ節の腫れ: 舌の異変と同時に、首のリンパ節が硬く腫れている。
白板症(はくばんしょう)と紅板症(こうばんしょう)について
これらは前がん病変と呼ばれ、将来的に口腔がんへと進行する可能性がある病変です。
-
白板症: 舌や頬の内側にできる、摩擦では取れない白い斑点です。痛みはほとんどありません。
-
紅板症: 粘膜にできる赤い斑点で、表面がなめらかであることが多いです。白板症よりもがん化率が高いと言われています。
これらの病変は、喫煙や飲酒が大きなリスクファクターとされています。定期的な歯科検診で早期発見することが非常に重要です。
口腔がんについて知っておくべきこと
不安を煽る目的ではなく、正しい知識を持つことで、不必要な恐怖をなくし、適切な行動をとれるように、口腔がんについて詳しく見ていきましょう。
1. 口腔がんとは?
口腔がんは、口の中にできるがんの総称です。舌、歯肉、頬の粘膜、口蓋(上あご)、口底(舌の下)など、様々な部位に発生します。日本での罹患数は年々増加傾向にあり、特に舌がんが最も多く発生します。
2. 主なリスクファクター
-
喫煙: 口腔がんの最大の原因と言われています。タバコに含まれる化学物質が粘膜を刺激し、がん化を促します。
-
飲酒: アルコールが代謝される過程でできるアセトアルデヒドが発がん性物質として作用します。
-
慢性的な刺激: 不適合な入れ歯や銀歯、とがった歯などが常に舌や頬の粘膜に当たり、慢性的な炎症を起こすことが原因となります。
-
ウイルス: ヒトパピローマウイルス(HPV)も、口腔がんの原因の一つとされています。
3. 治療方法
口腔がんの治療は、がんの種類、進行度、発生部位によって異なりますが、主に以下の方法が用いられます。
-
手術療法: がんを外科的に切除する方法です。早期発見できれば、切除範囲も小さく、機能温存が可能です。
-
放射線療法: 高エネルギーの放射線を当ててがん細胞を破壊します。
-
化学療法(抗がん剤治療): 抗がん剤を用いてがん細胞の増殖を抑えます。
早期に発見できれば、治療の成功率は非常に高く、口の機能や見た目を大きく損なうことなく完治を目指せます。
不安になったら、まずは歯科医院へ!専門医に相談すべき理由

「もしかしたら…」と不安になったとき、まず受診すべきは、いつも通っている歯科医院です。
1. 歯科医師は口の中の異変のプロ
歯科医師は虫歯や歯周病だけでなく、舌や粘膜の状態、噛み合わせまで、口の中全体を診る専門家です。口腔がんの初期症状や、その前段階の病変を早期に発見する能力に長けています。
2. 定期検診が最も重要
口腔がんの発見は、早期であればあるほど生存率が高まります。しかし、初期症状は痛みがないことが多く、自分自身では気づきにくいのが現実です。 虫歯がなくても、定期的に歯科検診を受ける習慣をつけることで、歯科医師が口の中の異変をチェックし、早期発見に繋がります。
3. 適切な医療機関への紹介
もし、歯科医師が口腔がんの疑いがあると判断した場合、速やかに口腔外科や大学病院など、より専門的な医療機関を紹介してくれます。不安な気持ちを抱えたまま、どの病院に行けばいいか悩む必要はありません。
日常生活でできる口腔がんの予防法

日々のちょっとした心がけが、口腔がんのリスクを減らすことに繋がります。
-
禁煙・節煙: 喫煙は口腔がんの最大のリスクファクターです。可能であれば禁煙を、難しければ本数を減らすだけでも効果があります。
-
節酒: 過度な飲酒は控えましょう。
-
バランスの良い食事: ビタミンやミネラルが豊富な野菜や果物を積極的に摂り、免疫力を高めましょう。
-
口腔内の清潔を保つ: 毎日の歯磨きを丁寧に行い、歯周病を予防しましょう。
-
慢性的な刺激を取り除く: 虫歯や欠けた歯、不適合な詰め物や入れ歯があれば、歯科医院で治療しましょう。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 舌に白いできものやぶつぶつがあります。口腔がんの可能性はありますか?
A. 舌に白いできものやぶつぶつができた場合、ほとんどは口内炎・舌乳頭炎・カンジダ症などの良性疾患です。特に痛みがあり、1~2週間以内に治る場合は心配いらないケースが多いです。
しかし、2週間以上治らない白い斑点(白板症)や赤い斑点(紅板症)、硬いしこり、痛みの少ないただれがある場合は、口腔がんの初期症状の可能性も否定できません。
「舌の白いできものが治らない」「痛くないのにしこりがある」場合は、早めに歯科口腔外科を受診することをおすすめします。
Q2. 口腔がんの初期症状にはどのような特徴がありますか?
A. 口腔がんの初期症状は、一般的な口内炎とよく似ているため見分けが難しいのが特徴です。
以下のような症状がある場合は注意が必要です。
-
2週間以上治らない口内炎
-
擦っても取れない白い斑点(白板症)
-
鮮やかな赤い斑点(紅板症)
-
舌や歯ぐきの硬いしこり
-
痛みが少ないのに治らない潰瘍
-
原因不明の出血やしびれ
口腔がんは早期発見であれば高い確率で治癒が可能です。少しでも違和感が続く場合は、自己判断せず専門医の診察を受けましょう。
Q3. 舌のできものは何科を受診すればいいですか?
A. 舌のぶつぶつや白いできものが気になる場合は、まず**歯科医院(特に歯科口腔外科)**を受診するのが適切です。
歯科医師は虫歯や歯周病だけでなく、舌や頬粘膜、口腔全体の粘膜疾患の診断を専門としています。必要に応じて、大学病院や総合病院の口腔外科・耳鼻咽喉科へ紹介いたします。
「いきなり大きな病院に行くのは不安」という方も、まずはかかりつけ歯科医院で相談することで、適切な診断と安心につながります。
Q4. 口腔がんを予防するためにできることはありますか?
A. 口腔がんは、日常生活の見直しでリスクを下げることができます。
特に重要なのは以下のポイントです。
-
禁煙(最大の予防策)
-
過度な飲酒を控える
-
毎日の丁寧な歯磨きと定期検診
-
合わない入れ歯や尖った歯の調整
-
バランスの良い食事で免疫力を維持
また、年に1~2回の歯科検診や口腔がん検診を受けることで、初期の異変を早期発見できます。
「症状がないから大丈夫」ではなく、予防と早期発見が最も重要です。
まとめ:大切なのは「放置しない」こと
舌にできたぶつぶつや白いできものに不安を感じたとき、最もやってはいけないことは「放置すること」です。
-
口内炎や舌乳頭炎など、ほとんどの場合は心配いらない良性のもの
-
しかし、2週間以上治らない、痛みがほとんどない、硬いしこりがあるなどの場合は要注意
-
自己判断はせずに、まずはかかりつけの歯科医院に相談する
不安な気持ちに蓋をせず、勇気を出して専門家に相談することが、あなたの健康を守るための第一歩です。名古屋市天白区のイナグマ歯科では、患者様のどんな小さな不安にも耳を傾け、丁寧な診断と分かりやすい説明を心がけています。
あなたの健康と笑顔を守るために、ぜひ一度ご相談ください。
【当院のご案内】
-
イナグマ歯科: 名古屋市天白区の歯医者・歯科・口腔外科・親知らずの抜歯治療
-
監修: 岡山大学 歯学博士 厚生労働省認定 歯科医師臨床研修医指導医 稲熊 尚広
-
ご予約・ご相談: [052-806-1181]または[予約フォームへ]から
【関連ページ】
イナグマ歯科の予約 →詳細はこちら
口腔外科のページ→詳細はこちら
唇のできもののページ →詳細はこちら
歯科定期検診 →詳細はこちら
口腔がんのページ→詳細はこちら